タイヤが均一なバランスでないと、部品の劣化が進み車両の寿命が縮みます。ドライバーさんが自分で行える「調整手順」もまとめたので、タイヤのチェックをしてみてくださいネ!!
タイヤのスリップサインは寿命のお知らせ
トラックなどの車両本体を安定させて走行するために、必要不可欠な部品であるタイヤ!
タイヤは日常的に走行していることで、少しずつ摩耗(磨り減り)が進んでいき、溝が減っていきます。
この溝が減っていることをドライバーさんに分かりやすく伝える目的で、ある目印があるのをご存じでしょうか?
「何それ?」「どんなマーク?」と聞いたことがない方へ向けて、全貌を大公開!
これがスリップサインです!!↓

スリップサインは、道路運送車両法によって定められている目印で、タイヤの使用限度(寿命)を明確にする重要な目的があります。
また、摩耗が進み溝の深さが1.6mmになった場合、トレッド面と高さが同じとなり、スリップサインが現れる仕組みとなっているのです…
スリップサインは、タイヤの構内にある盛り上がった箇所のことであり、トレッド全周の4か所~9カ所の範囲に設けられています。
なぜこのような目印があるのかというと、摩耗しているタイヤは事故を引き起こす可能性があるんです!
そのため、スリップサインが表面に現れたら、安全性を考えて「新しいタイヤに交換」する必要があります。
そこで今回は、スリップサインの見方・摩耗原因・タイヤを長持ちさせるコツなどについて、ワタクシ展子が調査した内容を詳しく解説していきます★
写真で解説!タイヤのスリップサインの見方
さて、タイヤはスリップサインが出ている状態と新品の状態で比較すると、溝の厚みに大きな差があります。
どれくらい違うのかというと「天と地の差」なのです!
 ※左がスリップサインの出る前・右がスリップサインの出た後の状態です
※左がスリップサインの出る前・右がスリップサインの出た後の状態です
また、タイヤのスリップサインの見方が、分からないという人も多くいるようで、「具体的にどこを見て判断するの?」という意見が寄せられています。
スリップサインは、タイヤ側面の三角マークが示す位置の溝の底にある盛り上がった部分のこと!

一般的にトレッド全周で4個~9個付けられているため、タイヤ一周の三角マークを確認すれば発見することができます。
また、摩耗することで溝が1.6mmになった場合は、法令で定められた溝の「最低ライン!」となるのです。
ちなみに、タイヤのスリップサインは、トラックや乗用車はもちろんですが、バイクのタイヤなどにもついているため、車両のサイズや規格に関わらずドライバーさんはこの目印に注意しなければいけません。
タイヤが均一なバランスでないと、部品の劣化が進み車両の寿命が縮みます。ドライバーさんが自分で行える「調整手順」もまとめたので、タイヤのチェックをしてみてくださいネ!!
続いては、タイヤスリップサインの車検時の合格ラインについて、触れていきたいと思います。
車検の合格ラインは何ミリ?タイヤの溝の深さ
車両の構造・装置・性能などを調べるために定期的に行う必要のある車検。
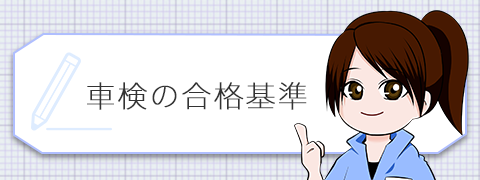
この車検では、車両全体を確認する訳ではありませんが、検査項目の一つとしてスリップサインの確認があります。
検査の際は、検査官がタイヤのトレッドから溝の間までを目視確認し、チェックをするのが一般的!
この確認時にスリップサインが出ていたり、保安基準である1.6mm未満ではないかと思われると、実測が行われることとなります…
これで溝の深さが1.6mm以上あれば「合格」となり、1.6mm未満の場合は「不合格」となるので要注意!
| 車検の合格ライン | |
|---|---|
| 溝の深さ 1.6mm以上 | 合格 |
| 溝の深さ 1.6mm以下 | 不合格 |
また、一般道路と高速道路を走行する場合では、車両ごとにタイヤの使用限度に差があるので以降で解説していきますね★
乗用車・軽トラック
タイヤの使用限度は、一般道路と高速道路で少し異なっているのをご存じでしょうか?
一般道路の場合は、全車両の使用限度が1.6mmと統一されており、車検の合格基準にもなっています。
一方、高速道路の場合は車両によって、使用限度がそれぞれ異なります!
これは一般道路よりも高速道理の方が、走行速度が速いことが関係しており、摩擦による抵抗が大きくなりやすいためです。

乗用車や軽トラックの比較的小さい車両は、高速道路でも溝の深さが1.6mmとなっており、一般道路と変わりはありません。
また、小型トラックや大型トラックの場合は、車両のサイズが大きくなるため、タイヤの使用限度が大きく変わります!!
小型トラック
お次は、小型トラックのタイヤの使用限度ついて、説明していきたいと思います!

小型トラックが一般道路を走行する場合は、タイヤの使用限度は1.6mmとなっています。
また、高速道路を走行する場合は、タイヤの使用限度が2.4mmとなっているので、これを下回らないように注意しなければいけません。
この車両ごとにタイヤの使用限度が定められている理由は、車両の重みと高速走行に耐えられる厚みが関係しているためです。
さらに、雨天の高速道路でも安全に走行できるために、溝の深さが決められています!!
雨天時に磨り減ったタイヤで走行した場合「ハイドロプレーニング現象」が起こる可能性があるためです!
この現象は水の上を滑ってしまい、ハンドルやブレーキが利かなくなるので、スリップして事故を起こしてしまう恐れがあるのです!
貨物を運搬するために使用されるトラックのタイヤは、基本的に頑丈に造られています!それでも、何らかの原因が重なり、事故につながる場合もあります。
大型トラック・バス用タイヤ
では、大型トラックやバスなどのタイヤの使用限度は、どれ程なのでしょうか?

やはり大型トラック・バスも一般道路の場合は、使用限度が1.6mmとなっています!
ところが、高速道路の場合は車両のサイズが大きくなっているため、使用限度が3.2mmとなっているのです。
大型トラックのタイヤは、沢山の荷物を積んで走るので、タイヤにも強度が求められるのです。
さらに、荷物を積載していない状態でも、車体本体が重たくなっているため、タイヤへの負担も増してしまいます…
このため、トラックのタイヤは形成しているカーカスコードを一層強化し、複数重ねて造られているのです。
タイヤのスリップサインを無視した場合の罰則
タイヤのスリップサインが現れているのにも関わらず無視した場合は、どのようなことが起きるのでしょうか?
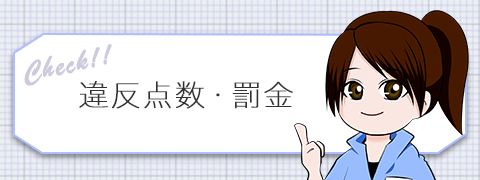
この時の症状としては、主に以下の3つが挙げられます。
| タイヤスリップサインの症状 |
|---|
| 1:走行性能が低下 |
| 2:ブレーキ性能が低下 |
| 3:雨天時の排水効果に変化 |
トラックのタイヤが摩耗すると、走行性能やブレーキの効きが低下するだけではなく、雨天時の走行では排水効果に大きな変化が出るのです。
これにより摩耗したタイヤでの走行は、安全性に「問題アリ」ということが分かります。
タイヤは溝の深さ、残り溝が1.6mmになるとスリップサインが現れますが、このままタイヤを装着し続けると「整備不良」と判断されて「道路交通法の違反」になることが考えられます…

ちなみに、スリップサインが1つ出てしまった時に「まだ大丈夫でしょ!」「他のタイヤは出てないし」と思った方へ!
一つでもスリップサインが現れた場合はアウト!
そのため、タイヤにスリップサインが出ている際は、以下の罰則の対象になる可能性があります。
- ■スリップサインを無視した場合の罰則
- ・違反点数
- ・罰金
違反点数
タイヤスリップサインの罰則の一つに、違反点数があります。
この違反点数は、タイヤのスリップサインが整備不良として判断された場合、点数が加算される対象となるのです!
違反点数は整備不良の点数で計算され、以下の通りになります。
| タイヤスリップサインの違反点数 | |
|---|---|
| 普通車 | 2点 |
| 大型車 | |
このようにタイヤにサインが現れたら、罰則の対象となるので早急に交換するように心掛けましょう。
罰金
次に、タイヤスリップサインの罰則には、罰金も設けられています!

これもタイヤスリップサインが整備不良としての扱われた場合に、違反点数と同時に罰則を受ける可能性があります。
ちなみに、罰金の対象車両・金額は以下が挙げられます。
| タイヤスリップサインの罰金 | |
|---|---|
| 普通車 | 9,000円 |
| 大型車 | 12,000円 |
乗用車・軽トラックなどの普通車両は9,000円となり、大型トラックなどの大型車両は12,000円となるのです!!
お次は、限界がきたタイヤの交換方法などについて、触れていくので引き続きご覧ください★
限界がきたら…タイヤ交換の方法ガイド
タイヤの溝にスリップサインが現れたら「限界がきた」という目印となり、サインが出た場合は「直ちに」「1日でも早く」タイヤ交換をする必要があります。

このタイヤとしての安全性能は「限りなくゼロ」に近い状態であるため、事故を起こす確率が高く、大変危険な状態なのです…
限界がくる前にタイヤを交換すると、事故防止に繋がるためオススメします◎!
早めの交換が大事ということじゃな!!
また、日頃からタイヤの整備・メンテナンスをしておくことで、思わぬトラブルを避けられるのです。
それでは、限界がくる前のタイヤ交換の目安について、ご紹介していきたいと思います。
| タイヤ交換の目安 | |
|---|---|
| ①走行距離 | 3~5万㎞ |
| ②経過年数 | 3~5年 |
| ③溝の深さ | 3mm |
まず、交換目安の1つである走行距離に関してですが、おおよそ3万㎞から5万㎞程度と言われています。
運転方法や使用している環境によっても変わりますが、この目安を覚えておけば、定期的に交換が行えるので覚えておきましょう!
2つ目の交換目安は経過年数で、大体3年から5年程度で交換を行うと良いとされています!!
これも走行状況などによって、摩耗の進み具合は変わるため年数に誤差があります。
最後の目安は、タイヤの溝の深さが3mmになったタイミングです。
これは、スリップサインが出る前であり、このタイミングで交換しておくことでスリップやハイドロプレーニング現象などを避けられる可能性が上がります!
また、タイヤ交換を行う場合は、ディーラーや整備業者などに依頼することが可能です。

自分(セルフ)で交換を行うことも可能ですが、工具の用意や場所の確保なども必要になるため、手間が掛かることを覚えておきましょう!
タイヤのスリップサインがでる磨耗原因
タイヤのスリップサインが現れる摩耗の原因は、どのようなことが関係しているのでしょうか?

この摩耗原因としては、主に以下の2つが挙げられます。
- ■タイヤのスリップサインの摩耗原因
- ・空気圧不足
- ・タイヤ周りのズレ
また、摩耗によるタイヤの減り方にも種類があり、基本的に以下の3つがあります!
- ■タイヤスリップサインの摩耗の種類
- ・ショルダー摩耗
- ・センター摩耗
- ・片側摩耗
タイヤは摩耗する原因によって、減る部位が異なっているということなんです!!
ここからは、タイヤの摩耗の種類や原因について、分かりやすくご紹介していきますね★
症状1:ショルダー磨耗
まず、1つ目の摩耗の症状としては、タイヤのセンター部分よりも両側のショルダー部分が早く減っていくショルダー摩耗。

この大きな原因は、空気圧の低下!
空気圧が低下している状態で走行することで、両端のショルダー部分が早く摩耗してしまう症状を引き起こすのです…
解決するための対策は、定期的な空気圧点検・空気充填を行うことで防止することが可能となっています◎。
- ●ショルダー摩耗の対策
- 空気圧点検・空気充填
症状2:センター摩耗
次に、2つ目の摩耗症状としては、トレッドの中心部分が早く磨り減ってしまうセンター摩耗があります。

このセンター摩耗の原因は、ショルダー摩耗とは逆で空気圧過多が大きく関係しています!
空気圧が高い状態での走行によって中心部分が盛り上がり、早く摩耗してしまう症状が表れるのです。
センター摩耗を防ぐための対策は、定期的な空気圧点検を行い、空気圧の値を調整しておくことが重要となります!!
- ●センター摩耗の対策
- 空気圧点検・空気圧調整
症状3:片側摩耗
3つ目にご紹介する摩耗の症状は、トレッドの片側のみが早く減ってしまう片側摩耗!

片側だけ減るなんて「どういうこと?」と率直に感じた方もいらっしゃいますよね?
トラックなどの車両は、普段何気なく運転していることが多いですが、道路から受ける振動によってタイヤ周りにズレが生じている可能性があります。
これにより真っ直ぐ走行していても、足回りのズレが影響して片側のショルダーだけが摩耗するという症状が現れてしまうのです。
このような摩耗を防止するためには、車両のアライメント調整行い、タイヤ周りのズレを正常に近づけることが大切です!
- ●片側摩耗の対策
- アライメント調整
タイヤを長持ちさせるコツ
最後の項目では、タイヤを長持ちさせるコツについて、皆様にご紹介させて頂きたいと思います。
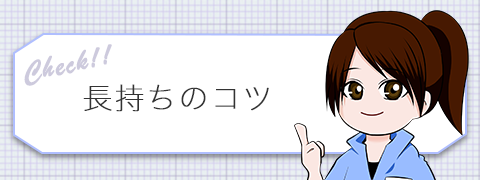
長持ちさせるコツやポイントはいくつかありますが、何よりもタイヤに負担を掛けないことが大切!
実践することでタイヤをより長く使用することができるため、覚えておいて損はありませんよ◎。
展子クン!
早く知りたいぞう!
まず、タイヤに負担がかかる走行方法は、以下の通りになります!
| タイヤに負担がかかる走行方法 |
|---|
| 1.急発進 |
| 2.急ハンドル |
| 3.急ブレーキ |
| 4.スピードの出し過ぎ |
運転する際に、上記の運転を防げばタイヤを長持ちさせる効果が見込めますよ!
特にスピードの出し過ぎは摩耗の進行を早めるため、制限速度の範囲内で一定の速度を保つようにしましょう。
また、走行方法以外にも、タイヤを長持ちさせるコツとして保存方法があります。
| タイヤを長持ちさせる保存方法 |
|---|
| 1.紫外線に当てない |
| 2.風・雨に当てない |
これらの保存場所は、風通しの良い車庫や室内に保管しておくといいトラよー。
さらに、遮光性や防水性のあるカバーを全体に掛けておけば、ホコリや結露から守ることができ、劣化などを防ぐことが可能に!
他にも、タイヤの空気圧点検を定期的に行うことで、摩耗・バーストを防ぎ、寿命を伸ばすことができるのです!
このような空気圧点検の目安は、1ヶ月に1回程度行うのがベストだと言われています!!
今回の内容は、トラックタイヤのスリップサインでしたが、皆様の理解は深まったでしょうか?
タイヤを長持ちさせるためには、日頃の整備・メンテナンスはもちろんのこと、適切な走行方法や保存方法が重要となります★
タイヤスリップサインまとめ
摩耗の原因や長持ちのコツを覚えておけば、タイヤをより長く使用することができるんですよ。
長持ちのコツがあったなんて初耳じゃったわ…
ところで…さっきから姫はうろちょろ何滑っとるんじゃ!?
あえてスリップサインが出ているタイヤに取り換えたみたトラー!!
滑りやすくなって楽しいトラァ~
トラック姫、危ないですよー。
事故は起こしてからでは遅いんです。
※皆様はくれぐれもマネをしないようにお気をつけください
タイヤが均一なバランスでないと、部品の劣化が進み車両の寿命が縮みます。ドライバーさんが自分で行える「調整手順」もまとめたので、タイヤのチェックをしてみてくださいネ!!
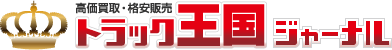

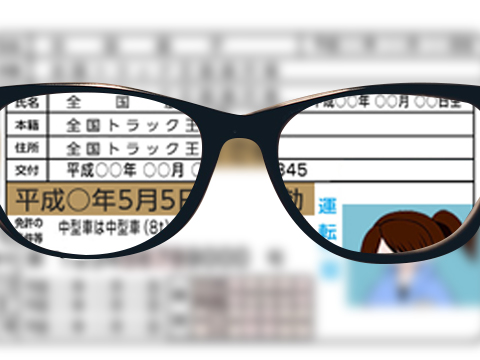

コメント
[…] らのサイトがりやすかったです→タイヤのスリップサインの見方を写真でチェック!車検不合格の限界は溝何ミリ? […]