トラックの荷台に、ユンボや重機などを載せて運ぶことが多いセルフローダー。
このセルフローダーを運転する際は、どんな免許や資格が必要でしょうか?
今回はセルフローダーの運転に必要な免許や資格について、まとめてみました!
セルフローダーとは?
セルフローダーとは、車や原付バイクといった単車、フォークリフト、その他建設設場などで使用される大型の重機などを運搬するためのトラックです。
セルフローダーは、トラックの前方部分をジャッキで持ち上げて、荷台部分を傾斜させ車両を積み込むのが主な特徴となります。
荷台後部分に『あゆみ板』を装着することにより、楽に地面から重機や車両を乗せたり、降ろしたりできるのが大きなメリットといえます。あゆみ板を荷台部分と段差部分に装着することで、荷台をスムーズに積み込めます。
また、あゆみ板には自動で動かせるタイプもあり、自動タイプであれば、作業の負担を減らしながら、よりスムーズに積み下ろしができるのがメリットとなります。
セルフローダーは基本的に重機、建設機械といった大きな車両を載せることを目的としています。そのために、ほとんどのセルフローダーは、中型または大型トラックが使用されることが多くなっています。作業現場等で使用される建設機械、重機、フォークリフト、事故車等は公道を走行することはできないため、セルフローダーが活用されています。
セルフローダーとセーフティーローダーの違い
セルフローダーはセーフティーローダーと間違えられることがあります。セルフローダーとセーフティーローダーは、使用目的や見た目がとても似ていることから混同されることがありますが、車両を積載する方法が異なる点が両車の違いになります。セルフローダーの場合、ジャッキで持ち上げて荷台(ボディ)部分を傾斜させることで、車両を積み込んでいきます。
一方でセーフティーローダーは、荷台がスライドし傾斜させて車両を積み込めることが特徴です。どちらも荷台部分を傾斜させるという点では同じなのですが、傾斜角度はセーフティーローダーのほうが緩やかです。そのことから、安全に積み下ろしできるためセーフティーローダーという名前になりました。セルフローダーはセーフティーローダーと比較すると、傾斜角度が急なので、両者の違いを把握しておくことが大切です。
また、セルフローダーという名前は、建設機械メーカーの株式会社タダノの製品名が定着したことで呼ばれていますが、別名キャリアカーとも呼ばれるのがセルフローダーなのです。ですので、キャリアカーといわれてピンとこない人でも、セルフローダーと言われれば分かるという方もかなり多いかもしれません。
セルフローダーの運転に必要な免許と資格
セルフローダーで公道を運転する際に必要となる免許と資格ですが、基本的に運転免許を取得していれば、セルフローダーを運転することが可能です。 運転免許には以下の条件があります。
車両重量5t未満・最大積載量3t未満→普通免許
車両重量8t未満・最大積載量5t未満→中型(8t)限定免許
車両重量5t~11t・最大積載量3t~6.5t→中型免許
車両重量11t以上・最大積載量6.5t以上→大型免許
セルフローダーは、最大積載量、車両総重量によって必要な免許、資格が異なるということを必ず知っておく必要があります。もし、あなたが条件に合った免許を取得していれば、セルフローダーを運転することが可能です。乗用車を積載するローダーの多くは4tクラスなので、中型免許以上が必要となることが多いのも事実です。
セルフローダーを運転してみたい、セルフローダーが走っている姿を見て「カッコいい」と感じたという方も決して少なくはないでしょう。そのような方の場合、運転に必用な免許があれば、ご自身でセルフローダーを走行させることができるのです。大型のトレーラー、トラック運転手に憧れがあるという人でしたら、セルフローダーがとても魅力的に感じるのではないでしょうか。
巻上げ機運転者の資格について
セルフローダーには、重機、建設機械、フォークリフト、事故車等さまざまなものを積み込みます。走行不能車両を積載する際には、ワイヤロープを使用し走行不能車両を荷台部分まで引き上げる必要があるのです。この作業で使う巻上げ機(ウインチ)を使用するには、巻上げ機(ウインチ)運転者という操作資格が必要となります。
巻上げ機(ウインチ)運転者の資格を取得する方法は、学科と実技2日間で行われる巻上げ機(ウインチ)運転特別教育を受講することです。この講習が修了すれば、巻上げ機(ウインチ)運転者の資格を取得できます。わずか2日間の実習で取得できることもあり、かなり手軽に取得できるのも魅力でしょう。
しっかりと出席をして講義を真面目に聞いていれば、この資格を取得するのはそこまで難しいことではありません。そして、使い方を教わることで、簡単に実践することができます。
それでも、正しく荷物を固定しなければ大きな事故につながってしまう可能性が高いために、取り扱いにはより慎重になる必要性があるのです。適切に操作し、積み下ろし、固定作業を行うことで、事故を起こしてしまう確率を大きく下げることができるでしょう。
セルフローダーの操作時には危険がつきものなため、正しく取り扱い、安全に操作を行うことがとても大切なのです。
セルフローダー運転時の注意点
セルフローダー運転時には、さまざまなことに注意しなければなりません。しっかりと荷物を固定した状態で走行しなければ、車両が地面に落ちたり、後ろを走行している車に落下してしまったりすることも考えられます。そうなると非常に危険ですし、死傷者が出てしまうことも考えられます。そのようなことが決してないように、セルフローダー運転時には、しっかりと荷物を固定して安全な状態で道路を走行しましょう。
また、急ブレーキや急ハンドルで危険な運転をしないようにしてください。ちょっとしたことで安定性が欠如してしまい、セルフローダー走行時に車両が落下してしまうことがあるのです。セルフローダーを運転する際には、常に安全に配慮しながら、適切に車両を固定して走行しなければならないのです。
そうしなければ、いつどこでどのような事故が起きてしまうかがわかりません。ですので、セルフローダーはそれだけ運転時に危険が多いということを知っておきましょう。また、セルフローダーは荷台を傾斜させることもあって、車両後方は十分なスペースを確保しなければなりません。車両を積み込んだ際も、車両がはみ出していないかを必ず目視して確認しなければいけないのです。
セルフローダーの制限外積載物について
万が一荷台に積み込んだ車両が車体全長の10%以上はみ出していれば、道路交通法違反になってしまい、罰則を受けてしまうことになります。そのようなことが起きないようにするためにも、10%以上はみ出してしまいそうであれば、前もって「制限外積載許可」を申請しておきましょう。
制限外積載許可の申請には、以下の書類が必要です。
制限外積載許可申請書
申請者本人の運転免許証のコピー
車検証のコピー
経路図
特殊車両通行許可証
これらを事前に用意しておくことで、問題なく許可を得られるでしょう。積載物の長さや幅、あるいは高さのいずれかが以下の数値を超える際に、制限外積載許可の申請が必要となるのです。
積載物の長さが車両の1.1倍となる場合
積載物の幅が車幅からはみ出した場合
積載物の高さが積載時に3.8mを超える場合(高さ指定道路の場合は4.1m)
制限外積載許可を取得すれば、基準を超えた場合でも積載することができます。ですので、荷物が10%以上はみ出すおそれがある場合、忘れずに制限街積載許可を申請しておいてください。これを申請しておくことで、罰則を受けずに済みます。
申請は、出発地管轄する警察署あるいは、交番、駐在所に申請します。セルフローダーを運転する場合には、これらのことに注意しながら、安全に運転することが何よりも大切なのです。
かなり面倒に感じるかもしれませんが、安全、そして、人々の安心のためには、しっかりと事前に許可を取っておく必要があるのです。これを行わなければ道路交通法違反となり、最悪の場合、免許をはく奪されてしまうことも考えられます。
重機、建設機器、バイク、車両等の大きな荷物を積載できるセルフローダーは、とてもニーズが高いものとして知られていますし、他の車両では果たせない大きな役割を果たしているのです。セルフローダーの正しい活用法により、私たちの安全は確保されます。もし、セルフローダーが古くなってきた場合や、少しでも故障の疑いがある場合には、早めに点検をしておいてください。
また、セルフローダーを使用しなくなったという際には、セルフローダーを売却することを検討してみてはいかがでしょうか?セルフローダーを売却することで、別の車両を購入する資金に充てることができます。
セルフローダーの運転についてまとめ
セルフローダーは、車両重量、最大積載量によって運転資格が異なるということを覚えておきましょう。セルフローダーはとても利便性が高く大きな荷物を運搬する際に役立つものですが、それだけに正しく活用しなければ危険性も多いので、注意が必要となるのです。車両のマメな買い替えも意識してみてください。
特に人気の車種、需要のあるセルフローダーならば、高値がつくことも多くあるのです。セルフローダーを乗り換える際は、買取サービスの「トラック王国」をまずは利用しておすすめです。
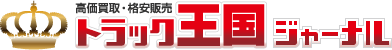



コメント