「長年使っているダンプは、トラックと比べて長持ちするのだろうか?」
ダンプを仕事で活用されている方の中には、このように思われることもあると思います。
また、ダンプに関するパーツの寿命も気になりますよね。
今回はダンプトラックの寿命や耐用年数、パーツ類の寿命について触れていきます!
ダンプとトラックの違い
では、ダンプとトラックはどこに違いがあるでしょうか?
ダンプの特徴は、荷台を動かして荷物(土砂やゴミなど)を降ろせることです。このため、荷物の積載と積み降ろしを1台で完結できます。ダンプの積み降ろしは英語でdumpと呼ぶことから、日本でダンプという名称が定着しました。
トラックの特徴は、貨物自動車として荷物を運ぶことです。貨物自動車はタンクローリーやミキサー車も含まれ、荷台を使い荷物を運ぶことを目的としています。
ダンプの寿命と耐用年数
では、ダンプの寿命と耐用年数は、どう分かれるでしょうか。以下では大きさ別のダンプの寿命、中古と新車の耐用年数などについて触れていきます。
寿命の目安
ダンプの寿命は、トラックの寿命と同等となっています。小型から大型までの年数は、以下のように分類されます。
小型ダンプ→10年
中型ダンプ→10年から15年
大型ダンプ→10年から15年
耐用年数の目安
次は耐用年数の目安について。耐用年数は「会計上の年数」と「使用限度としての年数」を表しています。
耐用年数は国税庁が定めていて、新車ダンプの耐用年数は新車登録から4年となっています。このため、4年以内と4年以降で耐用年数の算出方が異なります。
4年以内
4年以内であれば、耐用年数の残存期間が残っています。この際は「(法定耐用年数-経過した年数)+経過年数の20%」に相当する年数が、耐用年数として扱われます。
4年以内→法定耐用年数-経過した年数)+経過年数の20%
4年以降
新車から4年を経過したダンプは「法定耐用年数の20%」を、耐用年数として扱います。
4年以降→法定耐用年数の20%
ダンプの寿命の目安(走行距離)
では、小型・中型・大型までのダンプの寿命(走行距離)目安は、何キロでしょうか。目安の走行距離はトラックと同等であり、上記の年数と併せると以下のようになります。
小型ダンプ→10年・10万キロ
中型ダンプ→10年から15年・10万キロ〜50万キロ
大型ダンプ→10年から15年・70万キロ〜100万キロ
ダンプのパーツの寿命の目安
ダンプは様々なパーツを備えていますが、代表的なパーツの寿命はどうなっているのでしょうか?今回はクラッチとタイヤの寿命を確認しましょう。
クラッチ
ダンプのシフトチェンジに使うクラッチは、走行距離と使用年数によって寿命が定義されます。クラッチの寿命は、半クラッチのような状態が続くこと、トランスミッション(ギア)がつながりにくい場合などが続いた際、寿命の目安となります。
年数:5年~8年程度
走行距離:10万km以上
タイヤ
走行に欠かせないタイヤは、走行距離では3~5万km程度、年数では3〜4年程度が寿命の目安となります。これは、高速道路での走行やタイヤへの紫外線量、正規の空気圧での走行などによって変動します。
走行距離:3~5万km程度
年数:3〜4年程度
ダンプの寿命まとめ
ダンプの寿命について、ご理解いただいたでしょうか?また、寿命が近いづいたダンプをお持ちであれば、処分を検討されると思います。ダンプを処分する際は、対応の良い業者・高額査定を行う業者を探すことが大切です。高額で買取してもらえれば、新たなダンプも買いやすくなりますよね。
そんな場合は「トラック王国」のご活用をおすすめします。
「ダンプを高く売却したい」「まとめて車両を処分したい」という方にも対応できるので、お気軽にご活用してみてはいかがでしょうか。
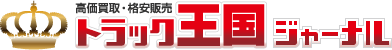



コメント